クロストーク:脱炭素DX
脱炭素社会の実現に向けた潮流の中で
システムの側面から脱炭素経営を支えること、それは地域貢献にもつながる
システムエンジニア Nさんサテライト事業部/サテライト1部/1課
プログラマー/システムエンジニアとしてキャリアをスタート。アクシスに転職後、フロント業務を担うSEとして従事。その後、10年以上、再生可能エネルギー関連の事業部門にてシステム営業、企画、マネジメントを歴任。今期より、建設DXを中心とする部門に異動、活躍が期待されている
プロジェクトマネージャー KさんSX事業部/エンジニアリング部/プロダクトユニット
2022年、アクシスに新卒入社。1年間の新人研修を経て、前身のオープンプロダクト部に配属。太陽光発電監視システム(以下、SPV)の保守運用業務を経て、自社プロダクト「ecoln」に関わる。一昨年より同プロダクトのSI案件においてプロジェクトマネージャー(以下、PM)を務めている
進行:広報担当
アクシスは、2011年の「東日本大震災」を機に再生可能エネルギーに舵を切る社会的背景の中、今後の可能性を鑑み、太陽光発電監視システム(以下、SPV)を自社開発、現在まで多くの太陽光発電所にSPVが導入されています。また、気候変動が社会的な課題となる世界的な潮流の中、2021年に脱炭素経営に必要な需給エネルギーの可視化を実現する自社プロダクト「ecoln」をリリース。現在は、OEMを中心に各社のニーズに合ったカスタマイズや一部の機能提供などを実施。今回は再生可能エネルギー事業の元マネジメントと、SI案件のPMを務める若手社員に話を聞いています。
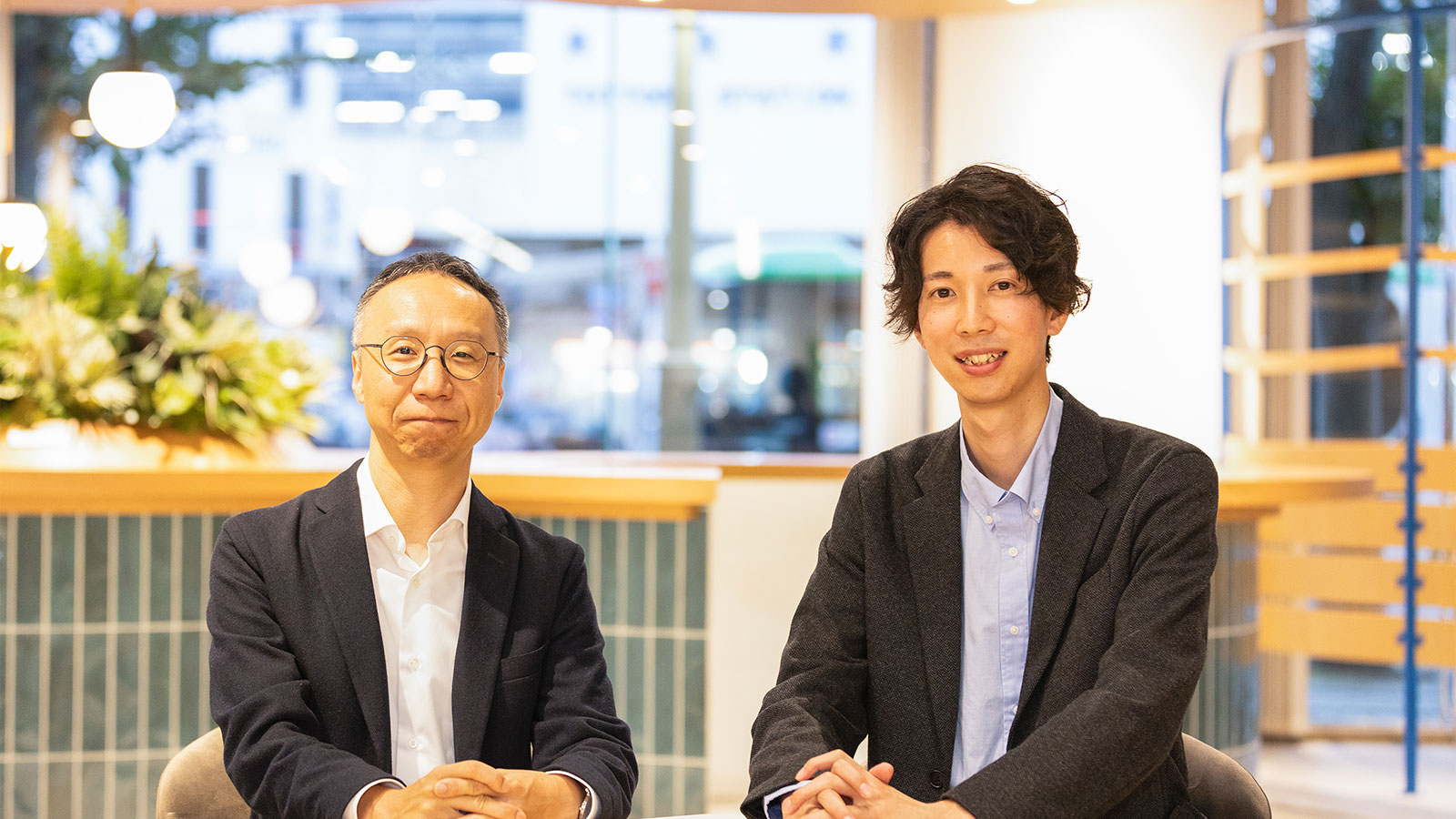
コードを書くよりも、
資料作成がメインとなった業務
- 広報
- 各企業の需給エネルギーの可視化や太陽光発電所の遠隔監視という業務においては、コードを書くという業務からは少離れることになったと思いますが、その辺りの変化は如何でしたか?
- N
- この分野の業務に関わる直前の業務は企画提案がメインで、しばらくコーディングから離れていた事もあり、特に抵抗はなかったです。
- K
- 確かにコードは書かない業務なので、入社前や研修当時に思い描いた「システムエンジニア」の仕事とは少し違いますが、私もあまり抵抗はありませんでした。
仮配属から10カ月ほどして、「ecoln」のプリセールスとして営業と技術の間の業務を担い、その後、要件定義や基本設計の部分を経験し、外部の業者や営業側との連携、品質管理を担う部門とのやり取りを集約するPMの役割を担っています。

専門分野の知識を得る以上に、
お客様のニーズを知る事が基本
- 広報
- 再生可能エネルギーや、脱炭素経営については世界的な動きや、国内動き、各省庁の制度や補助金の制定など業務を進める上で、必要になる知識も多いと思いますが、その辺りはいかがですか?
- K
- 「ecoln」に関しての知識が少ないこと、再生可能エネルギーや脱炭素経営に関する知識が決して多くはない中で、お客様やパートナーさんに質問することを、難しく感じていた部分はありました。新しい知識を得る、学ぶことは面白いと感じる半面、「知らない」と伝わる怖さもありました。
- N
- お客様の前で「知らない」とは言えないですし、知識量での不安はつきものですね。ただ、基本的にはお客様が脱炭素経営で抱えている課題や、目指す方向は何ですか?というスタンスが大事になります。もちろん、一般的な知識は必要なので、自身がマネジメントの立場にいた時には「今は、たまたまエネルギーに関わっているだけで、医療の仕事なら医療、建設なら建設とお客様によって知識を得ることが必要」と常々伝えていましたね。

品質管理体制という社内サポートがあるからこそ、
挑戦できた
- 広報
- 今回のプロジェクトを推進する中で、今後も続けていきたいことや、大切にしたいと思うことはありますか?
- K
- 「状況報告」ですね。社内にはプロジェクトの品質管理体制が整っています。そのプロセスの中で、定期的に品質管理の担当部門や担当役員に状況報告や相談ができたこと、また方向性の確認や修正に取り組めたことはプロジェクトを推進する上で大きな支えになりました。その事から「状況報告」を大事にしたいです。もう1つは、お客様との良好な関係性の構築です。
- 広報
- お客様との関係性の構築に向けて取組んだことはありますか?
- K
- 打合せの際にユーモアを挟むこと、と「言い切ること」です。「〜思います」ではなくて、わかることは伝え、わからないことは「持ち帰ります」と言い切るようにしていました。
- N
- プロジェクトは「終わらせる」ことが必要で、いただいた意見・要望の全てを実現できないケースもあります。この立場ならどうか、コストへの影響、違う方法はないかといった調整を、他者を巻き込みながら進めることは大変ですが、大きな経験、成長につながりますよね。
エネルギー分野もまた、
地域貢献につながる事業
- 広報
- 脱炭素経営に向けた世界の動き、日本国内の動きも変化していますが、今後この分野はどのように進んでいくと感じていますか?
- K
- おそらくビジネス規模は拡大して行くと思いますが、国の方針転換や法律の制定により大きく左右される分野ではあるので予測が難しいと感じています。
- N
- 基本的は伸びざるを得ない分野で、この先も再生可能エネルギーや脱炭素経営に向けた投資が続くと思います。ヨーロッパを中心に、上場企業は脱炭素に取組むことがルール化されていますし、日本でも始まることから各業界で対策が必要になります。需給エネルギーの可視化は取り組みの第一歩なので自社プロダクトとして各種システムを有していることは強みだと感じます。
電力を使うのは圧倒的に都会の人が中心ですが、その多くを地方の太陽光、風力等の自然エネルギーに頼っています。自然エネルギー資源を活かして発電し、マネタイズするにはシステムが活躍できることも多くあり、アクシスがエネルギーに関わる意義の1つです。鳥取には自然エネルギーも多くありますので、その意味では「Bird」と共に、地域貢献に繋がる事業だと考えています。
- 広報
- 今回リリースした「ごうぎんecoln」*はどのような点がこれまでと異なるのでしょうか。
- K
- 「ごうぎんecoln」とこれまでの「ecoln」一番の違いは、電力使用量の自動取込みが可能になった点と、「わかりやすく」という視点でカスタマイズした点です。本当に手間をかけない設計にしたことで、お客様に使っていただけるシステムとして育てていきたいです。
*「ごうぎんecoln」についてはこちら
